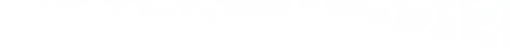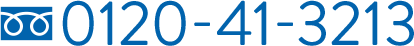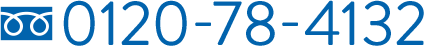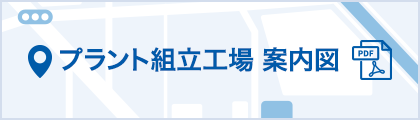レジオネラ対策に必要な洗浄・殺菌の方法!菌が発生しやすい箇所ごとに解説
- 水処理

レジオネラ属菌は、適切に洗浄・消毒が行われていない浴槽水や配管内で増殖しやすく、人体に取り込まれると肺炎など深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。
そのため、公衆浴場や温泉施設、病院や介護施設などの利用者が多い施設では、徹底した衛生管理が欠かせません。
そこで本記事では、レジオネラ属菌が発生しやすい浴槽設備の管理方法として、洗浄・消毒の必要性や発生を防ぐためのポイントなどを解説します。
また、万が一菌が検出された場合の具体的な対応手順についても紹介するので、感染リスクを最小限に抑えるための知識として、参考にしてください。
目次
レジオネラ属菌とは
レジオネラ属菌とは、自然界の水中や土壌に広く存在する細菌の一つです。20〜50℃の環境に生息可能で、最も増殖する温度が36℃前後だとされています。
また、汚れやバイオフィルム(生物膜、ぬめり、スライム)が存在する環境では、さらにその数を増やすという性質を持ちます。
このことからも分かるように、36℃前後の温度かつ、ぬめりが発生しやすい環境である浴槽周りは、レジオネラ属菌が繁殖するリスクが高いと言えるのです。
レジオネラが検出されやすい施設については後ほど詳しく解説しますが、銭湯や旅館、入院設備のある病院、高齢者施設などの浴場を提供している施設では、徹底した洗浄や消毒が求められます。
レジオネラ属菌が発生しやすい機器類を洗浄する必要性
全国各地の温泉や公衆浴場、入浴設備を持つ施設では、これまでに多くのレジオネラ症が報告されています。
レジオネラ症は、レジオネラ属菌を含むエアロゾル(水しぶき)を体内に取り込んでしまうことで発症し、レジオネラ肺炎やポンティアック熱といった感染症を引き起こします。
とくにレジオネラ肺炎においては、高齢者や免疫が低下している方の場合、重篤化して命に関わる危険性もある病気です。
したがって、レジオネラ症を防ぐためには、感染源であるレジオネラ属菌が発生しやすい浴槽、配管、循環ろ過装置内を徹底的に洗浄・消毒する必要があり、これは定期的に行わなければなりません。
なお、保健所長から営業許可を得て入浴設備を提供している施設においては、法令や行政指針によって、水質管理が義務化されています。
レジオネラ属菌が検出される可能性のある施設
以下のような水を多用する施設では、水温や水質の条件がレジオネラ属菌の増殖に適しており、レジオネラ属菌が発生するリスクが高いとされています。
- 公衆浴場
- 大型浴槽のある宿泊施設
- 遊泳プール等第三者の複数の人数が利用する施設
ここでは、それぞれの施設の特徴や発生リスク、法的な規制について解説します。
公衆浴場(公衆浴場法)
公衆浴場は、不特定多数の人々が利用するため、浴槽の水に汚れが溜まりやすく、菌が繁殖するリスクが高い施設です。
とくに浴槽水の循環ろ過システムを使用している場合、配管やろ過装置にバイオフィルムが形成され、レジオネラ属菌が増殖しやすい状態です。さらに、水温が40℃前後に保たれるため、レジオネラ属菌にとって最適な環境が整っています。
法的な決まりとしては、公衆浴場法で衛生管理基準が定められており、定期的な清掃や水質検査が義務付けられています。具体的には、以下の点が求められます。
- 浴槽水の塩素濃度を0.4mg/L以上に維持すること
- 定期的な配管の清掃および消毒作業を行うこと
- 水質検査を実施し、基準値(レジオネラ属菌が検出されないこと)を満たすこと
- 浴槽水を毎日完全に換水することが原則。毎日換水できない場合は、1週間に1回以上完全に換水
大型浴槽のある宿泊施設(旅館業法)
大型浴槽を持つ宿泊施設では、多数の宿泊客が利用するため浴槽水が汚れやすく、細菌が繁殖する条件が揃いやすい環境です。
また、施設の規模が大きいほど、循環系統が複雑化し、配管内での汚れが蓄積しやすくなります。そのため、清掃や消毒が不十分な場合には、レジオネラ属菌の繁殖が加速するでしょう。
法的な決まりとしては、旅館業法に基づき、宿泊施設は適切な衛生管理を行う義務があります。具体的には、以下のような管理が求められます。
- 浴槽水の塩素濃度やpHを定期的に測定し、基準値を維持すること
- 配管内の汚れを定期的に洗浄し、バイオフィルムの除去を徹底すること
- レジオネラ属菌の水質検査を行い、結果を公衆衛生機関に報告すること
遊泳プールなど第三者の複数の人数が利用する施設等
スポーツジムやレジャー施設のプールなど、第三者が多数利用する場所でもレジオネラ属菌の発生リスクは高いです。
とくに温水プールの場合はレジオネラ属菌が増殖しやすい環境なので、配管内やろ過装置に汚れが蓄積しやすく、細菌が急速に増殖します。
中でもシャワーヘッドやジャグジーのエアロゾルは、レジオネラ属菌を吸入するリスクを高めるでしょう。
なお、プールの衛生管理についての法律はありませんが、厚生労働省が提示する遊泳用プールの衛生基準では、水質基準や維持管理基準(水質検査の頻度など)が設けられています。
レジオネラが発生しやすい箇所の洗浄・消毒方法

入浴施設や設備でレジオネラを発生させないためには、単に浴槽を清掃するだけではなく、設備全体の洗浄と消毒が必要です。ここでは、レジオネラが検出されやすい箇所ごとに、洗浄・消毒方法を紹介します。
浴槽の洗浄・消毒方法
レジオネラ属菌は、入浴者の皮膚や土埃などを通じて浴槽内に持ち込まれることがあります。
とくに露天風呂や温泉などは外部からの汚染リスクが高いとされており、より厳格な管理が求められるでしょう。また、気泡装置やジェットバスなどの設備においてもエアロゾルが発生しやすい環境であるため、菌の拡散を防ぐ対策が不可欠です。
浴槽の衛生管理として、塩素消毒を適切に行うことが推奨されます。遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上を維持し、最大でも1.0mg/Lを超えないように注意しながら、毎日濃度を確認することが大切です。
さらに、週に1回以上は浴槽の水を完全に入れ替え、配管内部も含めて徹底的に清掃することが望ましいとされています。
また、レジオネラ属菌の自主的な水質検査も重要です。状況に応じて下記の通り、検査を行いましょう。
- 毎日完全換水する場合やろ過装置を使用しない場合:年に1回以上
- 連日使用するろ過装置がある場合:年に2回以上
- 消毒方法が塩素以外で行われている場合:年に4回以上
水質検査については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひチェックしてください。
関連記事:「レジオネラ属菌の水質検査について解説!発生しやすい環境と予防対策も」
循環配管の洗浄・消毒方法
循環配管内部にはバイオフィルム(生物膜)が付着しやすく、そのまま放置すると菌の増殖を助長する原因になります。
このため、定期的な清掃と消毒が必要です。
具体的には、まず、洗浄剤を使用して配管内部の汚れやバイオフィルム(生物膜)を除去します。とくにバイオフィルムはレジオネラ属菌の温床となりやすいため、物理的な洗浄や高圧水流の使用を併用すると効果的です。
洗浄後は、高濃度の塩素を使用して消毒を行い、遊離残留塩素濃度を5〜10mg/ℓに保つことが望ましいとされています。
この洗浄・消毒の処理は週に1回以上行うようにしましょう。
ろ過装置の洗浄・消毒方法
ろ過装置の管理では、装置の構造が複雑であるため、適切なメンテナンスを怠るとレジオネラ属菌が繁殖する危険性があります。
このため、定期的に清掃と消毒を行い、バイオフィルムが蓄積しないように注意することが重要です。
対策としては、入浴者の利用状況に応じてろ過装置の逆洗を週に1回以上行うことが推奨されます。また、遊離残留塩素濃度を5~10mg/ℓに維持し、週に1回以上の消毒を実施することで、安全性を確保することができます。
温泉水槽の洗浄・消毒方法
源泉の温度が60°C未満になると、バイオフィルムが形成されやすくなり、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高まります。
これを防ぐには、年に1回以上の清掃を実施し、汚れや菌の付着を防ぐことが求められます。
また、砂や異物の混入を防ぐために、適切なフィルターやカバーを設置することも効果的です。
オーバーフロー回収槽の洗浄・消毒方法
浴槽からあふれ出た水を回収し、再利用するためのタンクであるオーバーフロー回収槽は、適切な衛生管理を行わなければレジオネラ属菌が繁殖しやすい環境です。
そのため、オーバーフロー回収槽内部を常に清潔に保つ必要があり、回収槽の壁面の清掃と消毒を定期的に実施してレジオネラ属菌の繁殖を防止しなければなりません。
その際、塩素系薬剤などを使用して回収槽内の水を消毒するなど、適切な衛生管理を行いましょう。
具体的には、遊離残留塩素濃度を常に 0.4~1.0 mg/L に維持することを基本とし、少なくとも 1週間に1回 は回収槽を完全に排水したうえで壁面の清掃および消毒を行うことが求められます。
また、3か月ごと にレジオネラ属菌検査を実施し、不検出であることを確認することが推奨されます。
集毛器(ヘアーキャッチャー)の洗浄・消毒方法
集毛器(ヘアーキャッチャー)は、浴槽や排水設備に設置され、髪の毛やゴミを捕捉する装置です。この装置は非常に汚れやすく、湿気や汚れがたまりやすい環境にあるため、毎日の清掃が不可欠です。
まず、集毛器にたまった髪の毛やゴミを取り除き、目詰まりを防ぎます。次に、流水を使って付着した汚れを洗い流し、細かい部分の汚れについてはブラシを用いてこすり落とします。
洗浄後は、塩素系の消毒剤を使用し、消毒を行うことでレジオネラ属菌の繁殖を抑えましょう。
シャワー、カラン、ノズル部等の洗浄・消毒方法
シャワーやカラン、ノズルの内部も湿度が高く水が滞留しやすいため、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境となります。
とくにシャワーはエアロゾルを発生しやすく、吸入することで感染リスクが高まるため、公衆浴場では循環している浴槽水を使用しないことが定められています。
衛生管理の基本として、内部に水が滞留しないように定期的な通水を行うことが重要です。少なくとも週に一度はシャワーに通水し、内部の水を完全に置き換えることでレジオネラ属菌の増殖を抑えることができます。
さらに、シャワーヘッドやホースは半年に一度点検し、汚れやスケールの付着状況を確認しましょう。
レジオネラ予防に使われる洗浄剤と消毒剤について

一般的に、レジオネラ防止対策として塩素系の消毒剤が広く使用されていますが、それだけでは適切だと言えません。
まずはレジオネラの温床であるバイオフィルムの洗浄を行い、その後にレジオネラそのものを除去する消毒を行う必要があるのです。
ここでは、厚生労働省が推奨する洗浄剤と消毒剤について紹介します。
洗浄剤:過酸化水素
過酸化水素は強い酸化作用を持つ化学物質で、消毒・漂白・洗浄に広く使用される酸素系の洗浄剤です。
レジオネラ属菌の温床となるバイオフィルムは、細菌や微生物が集合し、ヌメリのある膜を形成することで、通常の消毒剤が浸透しにくい状態になります。このため、単なる塩素消毒だけでは除去が難しく、バイオフィルムをしっかり洗浄することが欠かせません。
そこで、強い酸化作用のある過酸化水素を2〜3%の濃度で約2時間循環させることで、有機物と反応した際に発生する泡がバイオフィルムを物理的に剥離・除去します。
さらに、過酸化水素はバイオフィルム内部に潜むレジオネラ菌にも作用するため、より高い除菌効果が期待できるでしょう。
消毒剤:次亜塩素酸ナトリウム
次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)は、レジオネラ属菌の消毒で一般的に使用される消毒剤です。強い酸化作用を持つ消毒剤で、主に水処理や衛生管理に使用されます。
水中に投入されると、次亜塩素酸(HOCl)と次亜塩素酸イオン(OCl⁻)に分解され、とくに次亜塩素酸が強力な殺菌効果を発揮します。この作用により、細菌やウイルスの細胞膜を破壊し、DNAやタンパク質にダメージを与えて死滅させます。
この薬剤は、レジオネラ属菌をはじめとするさまざまな病原菌の消毒に利用され、たとえば、大腸菌やサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、ノロウイルスなどにも有効です。
なお、消毒には主に塩素系薬剤が使用されていますが、他にも、オゾン、紫外線、銀イオン、銀・銅イオン、光触媒などの消毒方法もあります。ただし、これらの消毒方法は持続的な効果がないため、必ず塩素系薬剤と併用する必要があります。
レジオネラ属菌の消毒に適した濃度
レジオネラ属菌の消毒に適した塩素系薬剤の濃度は、入浴者数、浴槽の循環方式や設備の仕様、ろ材の汚れ具合、水質などによって変動します。
また、遊離残留塩素の消費量が一定ではないため、単に湯量(浴槽内・ろ過装置・配管内の総量)から添加量を決めるのではなく、実際に浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定しながら適切な量を調整しなければなりません。
次亜塩素酸ナトリウムの注意点
レジオネラ属菌の消毒に塩素を使用する際、水質によってはその効果が低下することがあります。とくに影響を与える要因として、水のpH値や有機物の存在などが挙げられます。
そのため、使用する際には、事前に浴槽水と塩素系薬剤の相互作用を確認し、適切な消毒方法を検討することが重要です。
| ●水のpH値と塩素の関係 まず、塩素は水のpH値によって効果が大きく変わります。最も効果を発揮するのが、ph6.8〜7.4程度とされており、pHが8.5以上になると、塩素消毒の効果はほとんどなくなってしまいます。 とくに温泉水を源水としている浴槽水では、pH値や温泉水に含まれる成分が影響を及ぼし、期待した殺菌効果が得られないことがあるため、注意が必要です。 |
| ●有機物と塩素の関係 水中の有機物(皮脂など)が多いと、塩素が消費されやすく、遊離残留塩素を十分に維持することが難しくなります。 その結果、殺菌効果が低下するため、事前に十分な清掃を行うことが大切です。 |
上記の他にも、浴槽の容量に対して温泉水の流量が多い施設では、塩素を投入しても短時間で流れ去ってしまい、効果的な塩素濃度を保つことが難しくなることがあります。
さらに、高濃度で使用すると設備の腐食や塩素臭が発生しやすくなるため、必要に応じてすすぎを行うなど、適切な管理を心がけることが重要です。
参照元:厚生労働省「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(全文)(令和元年12月17日時点)」
浴槽水からレジオネラ属菌が検出された際の対応手順
万が一、浴槽水からレジオネラ属菌が検出された場合は、施設の安全を確保し、感染リスクを防ぐために以下の手順に従って迅速かつ徹底的に対応することが求められます。
- 浴槽の使用を直ちに中止する
- 所管の保健所へ報告し、指示を仰ぐ
- ろ過器の逆洗と高濃度塩素処理を実施する
- 高濃度塩素処理後の排水と物理洗浄を実施する
- 浴槽および配管のすすぎと再給湯
- 再検査と使用再開の判断
① 浴槽の使用を直ちに中止する
利用者への健康被害を防ぐため、速やかに浴槽の利用を停止します。この際、利用者や関係者に状況を説明し、再開時期について適切に周知しましょう。
② ろ過器の逆洗と高濃度塩素処理を実施する
次に、ろ過器の逆洗を行い、内部に蓄積した汚れやバイオフィルムを除去してください。その後、浴槽水に塩素剤を投入し、遊離残留塩素濃度を10〜50mg/Lに調整して高濃度塩素水を作り出します。この高濃度塩素水を数時間循環させることで、浴槽、配管、ろ過器の内部を徹底的に消毒することが可能となります。この工程では、レジオネラ属菌の殺菌だけでなく、バイオフィルムが確実に除去されたかを確認することが重要です。
③ 高濃度塩素処理後の排水と物理洗浄を実施する
高濃度塩素処理が終了した後は、処理水を完全に排水します。この際、放流先の環境や水質汚染への配慮が必要であり、必要に応じて行政機関に相談しましょう。
排水後はブラシなどを用いて浴槽内を手作業で洗浄し、残留する汚れを物理的に除去します。
④ 浴槽および配管のすすぎと再給湯
洗浄後の浴槽や循環ろ過装置、配管内を十分にすすぎ、新たに給湯を行います。この際、遊離残留塩素濃度が0.4mg/L以上であることを確認し、安全な水質が確保されていることを確認してください。
⑤再検査
使用再開前に浴槽水のレジオネラ属菌検査を実施し、菌が検出されないことを確認します。もし再び菌が検出された場合は、最初の段階から同様の洗浄と消毒を繰り返しましょう。
なお、これらの手順は法令やガイドラインに従った措置として、専門業者や保健所と連携して実施することが推奨されます。
レジオネラ属菌の予防と発生時の対応はゼオライト株式会社にお任せください!
ゼオライト株式会社では、レジオネラ属菌の予防(発生リスク低減のための総合メンテナンス)や、早期対応(発生した場合の洗浄サービスなど)を実施しております。
レジオネラ属菌が発生した場合の洗浄サービスでは、まずは過酸化水素を使い、配管や濾過器などの手の届きにくい箇所もしっかりと洗浄、その後、塩素滅菌を行います。
発生リスク低減の総合メンテナンスとしては、継続して塩素滅菌を行い、確実に残留塩素が効くようにメンテナンスと調整をすることが重要です。残留塩素は常に0.4ppm程度をしっかりと効かせることで、レジオネラ菌が発生する温床を出来る限り無くすよう徹底しています。
レジオネラ属菌の対策に関する専門業者をお探しの事業者様はどうぞお気軽にお問合せください。
温浴施設等のレジオネラ属菌に関するご相談はゼオライト株式会社へ
ゼオライト株式会社は、水処理プラント及びメンテナンス事業を軸に、50年以上にわたってお客様の期待を超える「良質な水」と「メンテナンスサービス」を提供し続けてまいりました。
高い技術提案力とお客様第一主義の精神で、レジオネラ属菌にまつわるお困りごとを解決いたします。
【ゼオライトの実績】
- 浴場ろ過装置納入実績 150件以上
- 浴場ろ過 高濃度洗浄 年間100件以上
レジオネラ属菌の予防から早期対応まで、幅広い対応が可能です。
お気軽にご相談ください。