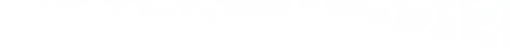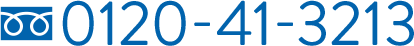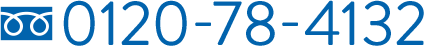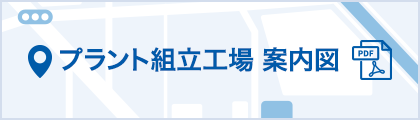レジオネラ属菌の水質検査について解説!発生しやすい環境と予防対策も
- 水処理

公衆浴場や温浴施設を管理する責任者の皆様にとって、利用者の安全を守ることは最優先事項です。その中で特に注意が必要なのが、「レジオネラ属菌」です。
この菌は、浴場循環系統の水や給湯設備、冷却塔などで繁殖しやすく、適切に管理されていない場合、肺炎の一種である「レジオネラ症」を引き起こす可能性があります。
本記事では、そんなレジオネラ属菌の定期的な水質検査の必要性や検査基準について分かりやすく解説します。また、菌が発生しやすい環境や感染経路、予防対策などの基礎知識もあわせて確認しましょう。
利用者に安心して施設を利用してもらうための信頼維持や法的義務への対応にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
レジオネラ属菌とは
レジオネラ属菌とは、土壌や河川、湖沼などの自然界に広く存在する環境細菌のことを言います。
これまでに60種以上が発見されており、中でも「レジオネラ・ニューモフィラ」という種類が代表的なレジオネラ属菌の1種です。
このレジオネラ属菌が、消毒が行われていない水や循環が少ない水、さらには水温が20℃〜50℃程度の環境に混入すると、増殖する可能性があるとされています。
そんなレジオネラ属菌について、発生しやすい場所や感染リスクについて確認しましょう。
レジオネラ属菌が発生しやすい設備
レジオネラ属菌は、20℃〜50℃の環境で生息可能で、最も繁殖するとされている温度は36℃前後です。
とくに湿潤でぬめりが発生する環境(バイオフィルム)で増殖し、以下のような人工的設備での発見が報告されています。
- 循環式ろ過装置や浴槽
- 給水や給湯設備
- 冷却塔
- 加湿器
- 温水プール
- 水景施設(噴水など)
これら設備の水質管理が不適切に行われると、レジオネラ属菌が内部で増殖してしまい、レジオネラ症という健康被害を引き起こす原因に繋がります。
そのため、入浴施設(公衆浴場や温泉施設、スポーツ施設など)や給湯設備を持つ施設(老人福祉施設や大規模な病院など)では、徹底した水質管理が求められるのです。
なお、レジオネラ属菌は塩素消毒をしても濃度や条件によっては死滅させることはできません。しかし、60℃以上の高温水に5分間さらされるとほぼ殺菌できるため、塩素消毒と高温水を組み合わせ、適切な管理が感染リスクを抑える鍵となるでしょう。
レジオネラ属菌が増える仕組み
レジオネラ属菌は、水回り設備で発生するバイオフィルムというぬめりの中に生息する「アメーバ」に寄生し、その内部で増殖する特性を持っています。
そしてアメーバの細胞内では約2時間ごとに分裂を繰り返し、24時間後には元の菌数の1,000倍にまで増えるとされているのです。
ここで、レジオネラ属菌が増殖する仕組みを詳しく確認しましょう。
|
上記から、アメーバが集まる巣窟であるバイオフィルムの中で、アメーバを宿主とするレジオネラ属菌が増えるということが分かります。
レジオネラ症
レジオネラ属菌に人が感染すると、レジオネラ症という重大な健康被害を引き起こします。
レジオネラ症には、大きく分けて重篤化する可能性がある「レジオネラ肺炎」と、一過性で軽症の「ポンティアック熱」の2つの型があります。
それぞれの型は特徴が異なり、原因や症状、進行具合も異なります。
①レジオネラ肺炎
レジオネラ肺炎は、感染症の中でも特に重症化しやすい疾患の一つです。
潜伏期間は2〜10日(平均4〜5日程度)とされており、高熱や咳、痰、呼吸困難などの呼吸器症状に加え、頭痛や筋肉痛、下痢、意識障害、精神神経系症状といった全身症状が現れることが特徴です。
発症後は急速に病状が悪化し、適切な治療を受けられない場合には死亡するケースも報告されています。
なお、抵抗力が低下している高齢者や病人、疲労やストレスで体力が落ちている人が発病しやすいとされているので、病院や高齢者施設ではより注意しなければなりません。
②ポンティアック熱
ポンティアック熱は、レジオネラ肺炎に比べて呼吸器症状は軽微で、重篤化することはほとんどありません。
潜伏期間は1〜2日(平均38時間程度)と短く、発熱や軽い咳、頭痛、筋肉痛といった比較的軽度の症状が現れるのが特徴です。
この型のレジオネラ症は自然治癒することが多く、通常は数日で回復します。
レジオネラ症の診断と治療
レジオネラ症の診断は、患者の症状や感染の可能性がある環境にさらされたかなどの履歴を基に行われます。
そして、診断方法には尿中抗原検査や痰の培養検査が用いられ、治療には主にマクロライド系やキノロン系の抗菌薬が使用されます。
レジオネラ症の感染経路
レジオネラ症の感染経路は主に、レジオネラ属菌で汚染されたエアロゾルを吸入することが原因です。
エアロゾルとは細かい霧やしぶきのことを指し、レジオネラ症の感染においては、浴槽水やシャワー水、冷却水などから発生します。
そのため、浴槽設備や冷却塔や加湿器、噴水といった人工水系環境の管理が不適切な場合、レジオネラの増殖が進み、エアロゾルに混じって体内に入ってしまうのです。
他の感染経路として、稀ですが汚染された水を口にしてしまうことで感染する場合もあります。
なお、人から人への感染は確認されていません。
レジオネラ属菌の水質検査が必要な理由

前述した通り、レジオネラ属菌が人体に入り込むとレジオネラ症に感染する恐れがあります。そのため入浴設備のある施設などでは、水質検査が欠かせません。ここでは、レジオネラ属菌の水質検査が必要な理由について、さらに詳しく確認しましょう。
施設の信頼維持のため
レジオネラ属菌の水質検査が必要とされる理由の一つに、「施設の信頼維持のため」があります。これは、施設が利用者に対して安全で安心な環境を提供することが、施設運営の基本であり、利用者からの信頼を得るために重要であるからです。
公衆浴場や冷却塔、噴水、医療施設の加湿器など、水を使用する設備を持つ施設では、レジオネラ属菌の繁殖が発生するリスクがあります。このような施設で適切な水質管理が行われていない場合、利用者や患者に健康被害を与える可能性があり、特にレジオネラ肺炎のような重篤な感染症を引き起こすリスクが高まります。
こうした事態が発生すると、施設の管理体制に対する社会的な批判や信頼の喪失に繋がり、失った信頼の回復には多大な努力と時間が必要となるでしょう。
このような事態を招かないためにも、施設運営者は衛生管理を徹底し、安全な環境を提供しなければならないのです。また、レジオネラ属菌の水質検査結果を公表することで、利用者に対する透明性を確保し、施設の安全性を強調することができるため、信頼をさらに高めることができるでしょう。
公的に定められているため
レジオネラ属菌の水質検査が必要とされるもう一つの理由として、「公的に定められているため」という点があげられます。
これは、法令や行政指針によって、水質管理が義務化されているということです。特に、公衆浴場や旅館業などの施設では、利用者の安全を確保するために水質検査が不可欠であり、その実施が法律や指針で明確に求められています。
例えば、旅館業法や公衆浴場法に基づき保健所長から営業許可を受けている施設では、各都道府県の条例によって、自主的な水質検査の実施が義務付けられています。
これに加え、厚生労働省が定める「旅館業における衛生等管理要領」や「公衆浴場における水質基準等に関する指針」では、浴槽水や冷却塔水のレジオネラ属菌検査を含む水質検査の基準が具体的に定められています。
この基準には、検査項目や基準値、検査頻度などが詳細に記載されており、施設管理者はこれに従って水質管理を行わなければなりません。
こうした法的な規定や指針は、利用者の健康被害を未然に防ぎ、施設の安全性を確保するために設けられています。特にレジオネラ症は重篤化する可能性がある感染症であり、感染のリスクを軽減するためには、適切な水質管理が不可欠なのです。
法令や指針に従って水質検査を実施することは、施設管理者にとって単なる遵守事項ではなく、利用者の安全と施設の信頼を守るための重要な責務といえるでしょう。
検査をしないと菌が増殖しているか判断できないため
レジオネラ属菌は配管内部やバイオフィルムなど、目視では確認が難しい場所で繁殖するため、通常の観察ではその存在が判断ができません。
また、水の見た目や臭いからの判断も難しく、たとえ水が清潔に思えても、実際には菌が含まれている可能性があるのです。
このような状況を見過ごすと、知らないうちに感染リスクが高まり、感染事例や集団感染が発生する可能性に繋がります。
そのため、専門的な水質検査を行い、菌が増殖しているかどうかを数値的に判断することが、レジオネラ症の発生リスクを回避するには欠かせないのです。
レジオネラ属菌の水質検査について

レジオネラ属菌が発生しやすい場所には、浴槽や給湯設備、冷却塔、加湿器、温水プール、水景施設などがあります。ここでは、最もレジオネラ症状による事故が多い浴槽と、その他の設備に分けて、水質検査の基準や頻度を紹介します。
レジオネラ属菌の水質検査:浴槽水
浴槽水の水質検査は、浴槽水のタイプに応じて、以下のように定期的に実施することが義務付けられています。この検査に関する書類は、少なくとも3年間保管しなければなりません。
| 浴槽水の種類 | 水質検査の基準 | 水質検査の頻度 |
|---|---|---|
| 循環ろ過器を使用していない浴槽水 | 10CFU/100ml未満 | 1年に1回以上 |
| 毎日完全換水型循環浴槽水 (ろ過しているが、毎日完全に完全に換水している浴槽水) |
||
| 連日使用循環型浴槽水 (浴槽水を24時間以上完全に換水せずに循環ろ過している) |
10CFU/100ml未満 | 1年に2回以上 |
| 連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 | 10CFU/100ml未満 | 1年に4回以上 |
※参照元:厚生労働省
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」
浴槽水は、ろ過器の使用の有無や、換水の頻度、消毒方法などで検査回数が異なります。これに合わせ、日常的な衛生管理も徹底し、事故が起こらないよう努めるようにしましょう。
なお、万が一事故が発生した場合、営業停止処分や罰則が科される可能性も考えられます。そのため、日常的に適切な衛生管理が行われているかを確認する目的でも、定期的な検査の実施は重要なのです。
レジオネラ属菌の水質検査:給湯設備・冷却塔・水景施設などの水
冷却塔水や水景施設など、直接エアロゾルを吸引する可能性の低い人口環境水の場合、水質検査基準と頻度は以下の通りです。
なお、頻度については目安であり、「新版レジオネラ症防止指針」の感染因子の点数化によって決まります。
| 設備等 | 水質検査の基準 | 水質検査の頻度 |
|---|---|---|
| 冷却塔 | 100CFU/100ml未満 | 1年に2回以上 |
| 給湯設備 | 10CFU/100ml未満 | 1年に1回以上 |
| 水景施設 | 100CFU/100ml未満 | 1年に2回以上 |
※参照元:厚生労働省「新版レジオネラ症防止指針(概要)」
また、基準ではありませんが、100CFU/100mlを超えた場合は、直ちに保健所に報告をし、清掃や消毒などの対策を実施しなければなりません。
その後は、菌数が検出限界以下(100CFU/100ml未満)であることを確認する必要があります。
レジオネラ属菌の発生を予防する対策
レジオネラ症は感染経路や症状が明確であるため、予防と早期対応が重要です。適切な水系設備の管理を徹底することで、その発生を大幅に抑えることができます。
レジオネラ属菌による感染を防ぐための対策としては、以下のような内容が有効です。
- 定期的な設備の清掃と消毒
- 水温管理(繁殖しやすい範囲を避ける)
- バイオフィルムの除去
- 給水設備の適切な流通管理
- pHの確認(アルカリ性が強いと塩素の効果が弱くなる為)
上記からも分かるよう、レジオネラ症を防ぐためには、レジオネラ属菌を「増やさない」「発生させない」「吸い込まない」という点がポイントとなります。
具体的な対策法として、温泉や冷却塔などの設備を定期的に清掃・消毒し、水温を20℃以下または50℃以上に維持することで菌の増殖を防ぐことが効果的です。
また、水の停滞を防ぎ、流れを確保することも感染リスクを低減する手段として有効です。
レジオネラ属菌の予防対策や洗浄方法については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひチェックしてください。
関連記事:レジオネラ対策に必要な洗浄・殺菌の方法!菌が発生しやすい箇所ごとに解説
レジオネラ属菌の水質検査は利用者の安全と施設の信頼にも欠かせません
本記事ではレジオネラ属菌がどのような特徴を持ち、人体にどのような影響を及ぼすかを説明しました。
レジオネラ属菌に感染してしまうとレジオネラ症を発症する可能性があるため、特に浴場設備のある高齢者施設や大きな病院などでは、水質管理の基準に則って定期的な水質検査をしなければなりません。
レジオネラ症の予防には、定期的な水質検査を行い、施設の安全性を確保することが重要です。
また、検査を行うことで、施設の信頼維持や公的基準への準拠といった管理者としての責務を果たすことにもつながります。
なお、私たちゼオライトでもレジオネラ属菌の検査を受け付けております。検査は専門の検査機関に依頼し、納期は10日〜20日程度です。また、レジオネラ属菌の発生リスク低減のための総合メンテナンスや、発生した場合の配管洗浄などを実施しています。安心・安全な施設運営のため、ぜひ依頼をご検討ください。
温浴施設等のレジオネラ属菌に関するご相談はゼオライト株式会社へ
ゼオライト株式会社は、水処理プラント及びメンテナンス事業を軸に、50年以上にわたってお客様の期待を超える「良質な水」と「メンテナンスサービス」を提供し続けてまいりました。
高い技術提案力とお客様第一主義の精神で、レジオネラ属菌にまつわるお困りごとを解決いたします。
【ゼオライトの実績】
- 浴場ろ過装置納入実績 150件以上
- 浴場ろ過 高濃度洗浄 年間100件以上
レジオネラ属菌の予防から早期対応まで、幅広い対応が可能です。
お気軽にご相談ください。